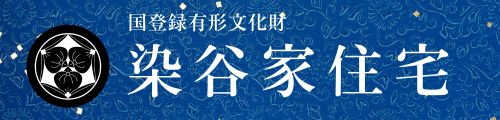『染谷家住宅とその周辺を巡る歴史探訪(春)』開催
こんにちは。春めいた暖かい日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
先日、4月20日(日)に『染谷家住宅とその周辺を巡る歴史探訪(春)』が開催されました。
当日は風が強い日ではありましたが天候にも恵まれ、12名の方々が参加してくださいました。ありがとうございました。
コースは我孫子駅からスタート。


当日ガイドをつとめてくださったのは、この地域の植物や歴史にとても詳しい高橋昌代さんです。
我孫子駅をあとにした一行は、岩井の貝塚、パッチワークの丘を探訪。
実はこの「パッチワークの丘」という名前は高橋さんが命名したのですが、とても素敵な名前ですよね。この丘は、さまざまな農作物が植えられ、その様子がパッチワークのように広がっていることから名前が付きました。
この場所は、昔、手賀沼の水草を肥料にしていたようで、そのことが手賀沼の富栄養化を防ぎ、きれいな水を保つことにも繋がりました。

『パッチワークの丘』の地形について解説する高橋さん。

奥に見える林の向こう側は、手賀沼。20メートルの落差があるようです。
次いで、一行が向かったのは鷲野谷地区に古くからある、浄土宗東光山 医王寺。
運よく、この日は医王寺の奥さまがいらしゃって、本堂にあがらせて頂きました。

本堂では、お釈迦さまの誕生を祝う花見堂(誕生仏)が置かれ、参拝するとともに灌仏(かんぶつ)をさせて頂きました。
灌仏会(かんぶつえ)とは、別名「花まつり」「降誕会」などとも言われ、お釈迦さまの誕生をお祝いする仏教三大行事(降誕会・成道会・涅槃会)の一つです。
お釈迦さまが誕生した時、九つの頭を持つ龍が降りてきて、甘露の雨を注いだと言われていることから、花見堂の中には甘茶が入れられ、それを誕生仏にかける(灌仏)をします。
なお、お釈迦さまは生まれてすぐ四方に7歩ずつ歩み、右手で天を、左手で地を指さし「天上天下唯我独尊」といったと伝えれれています。
因みに、お釈迦さまの誕生日は4月8日。医王寺の他、全国のお寺などでは同じように花見堂を出しお祝いをします。
医王寺をあとにした一行が向かったのは「十九夜(じゅうくや)信仰」の石碑を見学。

「十九夜」は毎月19日の夜に女性だけが集まり、安産、子育て、女性の病気の回復を祈願しました。本尊は「如意輪観音」。この鷲野谷ではこうした豊かな集まりがあったことを高橋さんから教えていただきました。

なかには赤子を抱いている観音さまがいて、一体一体の如意輪観音さまのお顔がとても優しくほほえんでいます。
探訪は、染谷家住宅はもちろん、色々な場所をめぐります。一部ですがご紹介させていただきました。



探訪すると、自然、歴史がゆっくりとした時間のなかで楽しく学べます。(ヤマブキ、シバザクラ、ライラック)
次回の『染谷家住宅とその周辺を巡る歴史探訪(春)』は5月18日(日)を予定していますが、おかげさまで満員御礼。
申し訳ございません。また、ご案内できるときを楽しみお待ち頂けましたら幸いです。